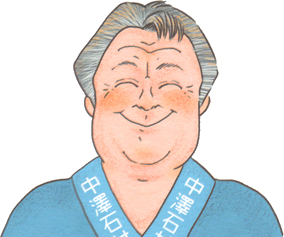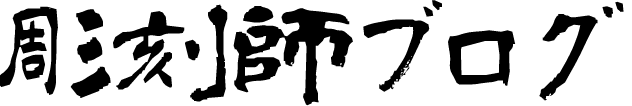富士山の美しさの秘密は“石”にあり
2024年6月30日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
7月の初旬、富士山の山開きが行われます。富士山は日本一高い山であるとともに、その円すい形、左右対称という形状の美しさにより、日本の象徴ともされるとても人気の山です。コロナ明けは、多くの外国人観光客も登山に来るなど、大変な混雑ぶりで話題になっていますね。

なぜ富士山はあのような形になったのでしょう。その理由の一つは、富士山をつくる玄武岩にあります。富士山は4階建ての構造になっていると言われています。富士山は火山であり、数十万年もの間、噴火を繰り返し、1万年前にようやく今のような姿になりました。
数十万年前の「先小御岳」「小御岳」までは粘性の強い安山岩やデイサイト、玄武岩からできており、形も今の富士山とは違っていたそうです。

10万年前に活動を開始した新富士の原型である「古富士」、1万年前から現在表面に見えている「新富士」となって現在の富士山の形になりますが、これらは玄武岩でできています。重要なのは、玄武岩マグマの「粘性が低い」という性質。「古富士」以降、つまり約10万年にわたり噴出し続けてきた玄武岩のマグマは粘り気が弱く流れやすかったため、裾野まで薄く広がり、徐々に今の美しい富士山を形づくってきたのです。

我々石屋に馴染み深い玄武岩といえば、六方石という石があります。これは玄武岩の溶岩が冷却し収縮する時に出来た、断面が五角形や六角形の柱のような細長い石材です。
その独特な色合いと形状の面白さから、庭石などに使われています。灯篭として加工されたり、おしゃれな彫刻を施されたオブジェとしても作られていますので、名前は知らなくともどこかでご覧になられているかもしれません。(当店でもご案内できます。ご興味がありましたらお問合せ下さい。)
富士山の景観や、六方石といった、人間の想像力を超えた絶妙な形を作り出す地球の力には驚かされますね。
硬~い花崗岩にも弱みあり!?
2024年5月31日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
しとしとと雨が降り続く梅雨。この時期に新緑が鮮やかさを増すように、雨に洗われた墓石の姿もまた美しいもの、土砂降りの雨でもなんのそのです。
日本の墓石に使われていることの多い“花崗岩”は、鉱物の中でもとくに硬い石英を多く含んでいるため、様々な石に比べて風化しにくいと言われています。こんなに硬い石は、何にでも強いと思われるかもしれません。

ところで、木曽川の名勝、寝覚の床に代表される花崗岩特融の地層の中には、自然の景観にも関わらず、まるで人工的に作り出されたような切り立った崖と平らな面で出来た大きな箱を並べたような不思議な地形があります。

これは、木曽川の激流が花崗岩の岩盤を長い年月にわたって浸食してできたものですが、ここから、花崗岩には、3方向の直行する割れ目ができやすいという特性(=弱点)が見えてきます。
私たち石屋は、こうした石の割れやすい方向を「石目」と呼んでいます。かつて人力だけで巨大な石を切り出せたのは、この「石目」を昔の石工達も知っていたから。

大きな石を割るには、まず一直線状にいくつかの穴を開け、「セリ矢」と呼ばれる金具を差し込みます。矢の頭を叩くうちに徐々にヒビが入り、あるとき一気に割れます。機械化が進み手作業は少なくなりましたが、石の産地で開かれるイベントなどで実演があると、見事な石の割れぶり(?)に歓声が上がるほどです。
逆に加工・施工の時は角が欠けないようにとても気を使います。石屋の仕事は豪胆さと繊細さの両面が求められます。みなさんもお墓参りの時は、墓石を傷つけないようにお気をつけくださいね。
小石に秘められた生命誕生の歴史
2024年4月30日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
2020年12月、小惑星探査機「はやぶさ2」のカプセルが、出発から6年の歳月を経て地球に帰還しました。予定通りカプセルを回収することに成功、中には小惑星「リュウグウ」で採取された小石や砂が入っており、プロジェクトのミッション成功が大きな話題となりました。地球から約3億キロ先にある小さな星にあった石のかけら、実は私ども石屋としても興味深いものです。

太陽系※1が誕生したのは遥か46億年前のこと。ガスや塵が集まって太陽が生まれた後、「リュウグウ」のような小惑星が生まれます。それが衝突・合体を繰り返して地球のような惑星が出来ました。
今回「リュウグウ」で採取された小石を調べることで、我々石屋が普段お世話になっている大地から掘り出された石の誕生についても、新たな発見があるかもしれません。
※1:太陽とその周りを周回する惑星などの天体で構成されている天体の集団。

さらにこの調査では、リュウグウには有機物(炭素を含む化合物)や水を含む鉱物が多く存在すると考えられることから、地球の水はどこから来たのか、生命を構成する有機物はどこでできたのかなど、生命の起源の解明に一歩近づける可能性があります。小さな石には、壮大な宇宙の記憶が秘められているのですね。

「私たちはどこから来たのか」という生命そのものの起源を解き明かしたいという欲求。それは途方もない話題のように思われるかもしれませんが、先祖と向き合うことで生命の大切さを実感し、自分のルーツに立ち返るお墓参りとも通じるものが…なんて思うのは、石屋だからかもしれません。
2024年の現在、はやぶさ2は新たな宇宙探索の旅へ出ています。数年後にはまた嬉しいニュースが聞けるといいですね。
野球少年が願いを託す聖地
2024年3月31日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
世界で活躍する日本人!といえば、今話題のメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がいます。
投手と打者の二刀流でアメリカの野球界を席巻し、昨年はシーズンMVPにも選ばれました。21年以来2年ぶり2度目の受賞となり、大リーグ史上初、前回に続き満票でのMVP選出。同じ日本人として、とても誇らしいですね。

一方で期待されながらも受賞に至らなかったのがサイ・ヤング賞です。これは大リーグの年間最優秀投手に贈られるもので、全米野球記者協会に所属する記者の投票によって選出されます。
サイ・ヤングは1890〜1911年まで活躍し、歴代最多の511勝を挙げた投手です。
「サイ」は、188cmの長身から投げ出されるボールが、サイクロン(暴風)のようにうなりをあげる剛速球だったということから付けられたニックネームです。

ヤングのお墓はアメリカのオハイオ州にあります。5月の最終月曜日の「メモリアルデー(戦没将兵追悼記念日)」に、ボールを供えると野球が上達すると伝えられ、多くの子どもたちが訪れるそうです。彼に敬意を表して作られたサイ・ヤング・メモリアル・パークには記念碑もあり、彼の功績を伝えています。

私たち石屋は、石のボールを置いたお墓、大会優勝の記念碑など、野球にちなんだお仕事や、その他にもたくさんの出来事や功績を後世に伝える事に携わることがあります。込められた想いや記された記録はどれも素晴らしいもの。
新しいことを始める際はその道の先人のお墓や記念碑を訪ねて上達を願ってはいかがでしょうか。大谷選手もアメリカで、歴代名選手のお墓を訪ねたかもしれませんね。
地球上で最古の花木 ~木蓮~
2024年2月29日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
だんだんと暖かくなってきましたね。今日は春になると桜とともに美しい白色や紫色で街中を彩る「木蓮-もくれん」の話題をお届けします。「木蓮」は「マグノリア」の名前でも有名ですね。空に向かって大きな花をたくさんつける花木で庭木や街路樹としても人気があります。

木蓮の名前は「蓮(ハス)」という花に似ていることに由来しています。この蓮という花は仏教に関わりが深く、仏や慈悲の象徴とされています。そんな蓮に似た花を咲かせる木蓮は「天国に咲く蓮の花」とも言われ、中国では寺院や宮殿などに木蓮を植える風習があるそうですよ。
木々に大きなつぼみがたくさんついた姿は、まるでたくさんの小鳥がとまっているように華やか。開花時期に近寄ると、上品で優雅な甘い香りを楽しむこともできます。

つぼみの先が一斉に北を向くことから、方向指標植物(コンパス・プラント)とも言われています。つぼみがふくらんだ木蓮を見つけた時はちゃんと北を向いているか、確認してみるのも楽しいですね。
原産地は中国南西部。もともと中国では漢方として扱われており、日本にも平安時代以前に頭痛や鼻炎の薬として伝わりました。

また、木蓮は地球上で最古の花と言われています。恐竜が活躍していた白亜紀の地層からモクレン属の化石が発掘されており、1億年以上も前から今と変わらぬ姿で咲き続けているそうですから、とても興味深いですね。その花の大きさや独得のカタチは恐竜たちにぴったり。恐竜たちにとって春の花と言えば木蓮だったのかもしれないと思うと、面白いですね。
大海での大冒険を伝えるお金、石貨
2024年1月31日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
今年の7月、20年ぶりに新紙幣が発行されます。紙幣に描かれた歴史的著名人も新デザインと共に変わります。 長く慣れ親しんだ1万円札に描かれていた福沢諭吉は「近代日本経済の父」とされる実業家の渋沢栄一になります。2021年に放送したNHK大河ドラマの主人公にもなりましたね。彼は明治初期、出来て間もない大蔵省で日本の近代的貨幣制度を整備しました。この時、私達が普段使っている「紙幣」「円形の貨幣」が誕生したのですが、世界を見渡すと、様々なお金があります。

中でもミクロネシア連邦のヤップ島の巨大な石貨については、一度は聞かれたことがあるのではないでしょうか。
「石のお金」といっても日常の買い物で使うのは米ドルで、石貨は主に冠婚葬祭の儀礼的贈答品や土地の売買などで使用。そのサイズは様々で直径が1~3mという大きなものは、置かれたまま所有権のみが移行するそうです。石貨と名がついているくらいなのでお金としてその昔に流通していたのだろうと思いきや、現在でも使われているというのだから驚きですね。

石貨は20世紀前半までつくられていました。素材はヤップ島では採れない石灰岩で、500km先のパラオ諸島まで出向き、石を切り出して加工。長い航海の末に持ち帰りました。
石の運搬は現代の技術を用いても大変な作業です。まして、数トンもの石を運ぶのは小さなカヌー。太平洋の孤島への復路は、かなりの危険が伴ったはずです。石貨には、そうした大冒険の記憶が刻まれているのです。

「石貨」は島に届くまでの苦労度が高いものほど価値があるそうですが、日々、石と向き合っている石屋としては大いに共感するところがあります。 石貨の実物は東京の日比谷公園や貨幣博物館等、日本でも見ることが出来ます。加工や運搬の苦労に思いを馳せてもらえると嬉しいですね。
石が生み出す迫力の建築物
2023年12月31日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
明治以降、国会議事堂に代表されるようにランドマークとなる建物には石、それも日本の風土でも耐えられる花崗岩が多く使われてきました。今回は、新しい年のはじまりに、力強さを感じられる石の建築物の話をしたいと思います。

平成に建てられた石の建物でよく知られているものと言えば、東京都庁ではないでしょうか。平成2年に完成した当時はサンシャイン60を抜いて日本一の高さとなり、東京の観光名所の一つとして、令和の現在も人気があります。高さ243メートルに及ぶ外壁にはスペインやポルトガル産の花崗岩が使われました。石の色の違いで表現された直線的で緻密なパターンについて、設計者の故・丹下健三氏は「コンピュータチップ」を表現したとコメントしました。

そして、時代は令和。2020年8月には埼玉県所沢市に隈研吾氏による『角川武蔵野ミュージアム』がオープンしました。高さ30メートルの建物の外壁には、1200トンもの中国産の花崗岩が使われています。
表面の凹凸を残した「割肌仕上げ」を採用し力強さを演出。61面体の建物は武蔵野の土地から湧き出てくるマグマをイメージし、大地からそそりたつ巨大な岩のような建物です。

垂直に伸びる直線で構成された都庁と、多面体で自然物のようなミュージアム。異なる二つの建築には、それぞれの時代の空気感が表れているようです。石も使い方によって大きく印象が変わることにも驚かされます。そんな石の魅力を感じられる建物が増えていくと石屋としても嬉しいですね。
お釈迦様が見守っている!?「大丈夫」
2023年11月30日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
日常の様々な場面で聞く「大丈夫」という言葉。現在では「あぶなげない」ことや、「間違いがない状態」「問題がない状態」という意味でよく使われていています。濁音が3つも含まれていて、力強い響きに安心感を抱きます。「大丈夫!なんとかなるよ。」と相手を励ましたり、自分を奮い立たせたりする場面にもよく使われていますよね。

この「大丈夫」という言葉は、もとは中国の言葉です。「丈」とは元々1メートル80センチという成人男性の身長を基準にした身体尺でした。「夫」は「おっと」という意味ではなく「男性」という意味で、「丈夫」とは「一人前の男性」を表していました。その中でも強くて立派な男性に「大」をつけて「立派な男子」を表すようになりました。そこからそのような立派な人が近くにいてくれれば安心だということから現在の「大丈夫」という意味に転じたそうです。

また、この「偉大な人、りっぱな人、しっかりした人」という意味を持つ言葉が仏教に取り入れられ、仏教用語では「大丈夫」は「お釈迦様」の別名としても使われるようになりました。意味を知ると、「大丈夫!!」と使うたびに、お釈迦様が見守ってくれているような気がしてきます。

折しも、年明けには入学試験シーズンの到来です。受験生の皆さんにも、「大丈夫!!」とあらためて送ってあげたいですね。
石碑が伝える疫病の終息
2023年10月31日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
長かった新型コロナウィルス感染症の流行も、ようやく落ち着きはじめました。旅行やイベントも開催されるようになり、以前の日常を取り戻しつつあります。今はまだ、しっかり「終息した」とまでは言えない状況ですが、その昔、世界中で猛威をふるった幾多の感染症も終息していったように、新型コロナウイルスもきっとその時を迎えることでしょう。
世界各地にはそういった疫病の流行について記された石碑が多く建てられています。
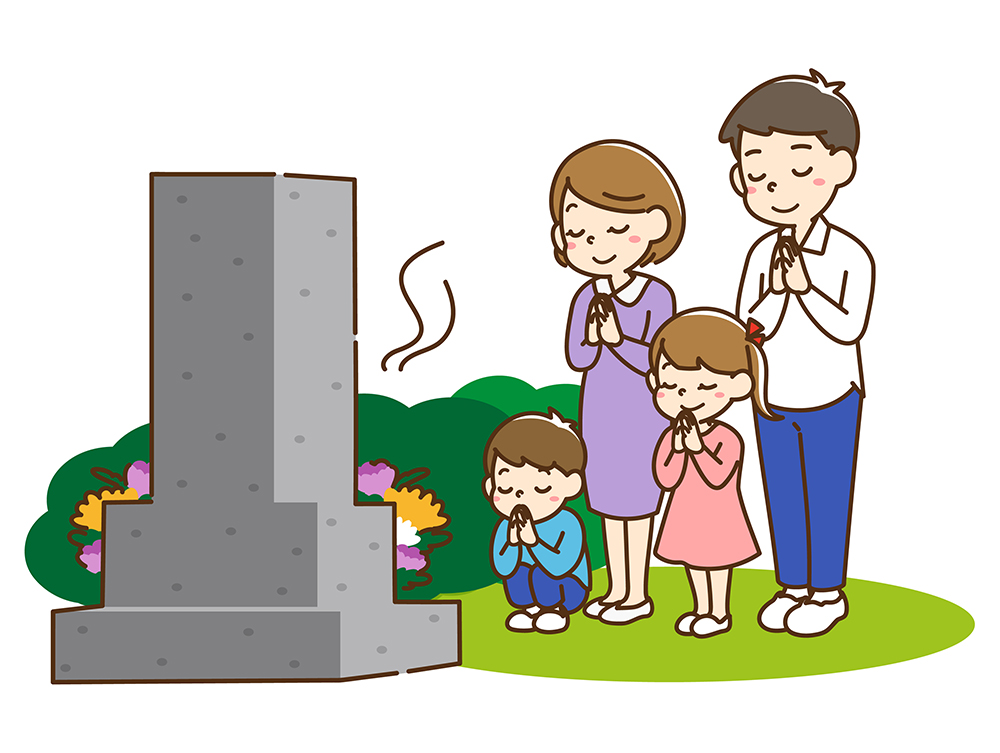
例えば日本の例では、江戸時代の文政5(1822)年、日本で最初にコレラが流行し、明治時代には数年ごとに大流行を繰り返し、明治時代の45年間の死者は全国で約37万人にも上ったと言われています。全国各地で流行したことから、供養碑も全国各地に建てられています。
埼玉県越谷市の安国寺には、江戸時代の安政6年(1822)建立のコレラ供養碑があり、当時の様子を碑文に残して、亡くなった人々を供養しています。

また、ヨーロッパ各地にはペスト終息の記念碑があります。
有名なのが1694年に建てられたオーストリア・ウィーンの「ペスト記念柱」です。この記念碑は、ペストの終息とオスマン軍との戦いに勝利したことを記念して、皇帝レオポルト1世が建立しました。大理石製で上部にはキリスト教の三位一体像が輝き、擬人化されたペストを天使が退治しているシーンも。日本の石碑とは意味が異なりかなりゴージャスですが、ペスト終焉の証を今に伝えています。

このコロナ禍で疫病退散の妖怪として注目を集めたのが、「アマビエ」。早く終息するようにとの願いを込めて、アマビエの石像があちこちに立てられました。これまで数々の疫病を乗り越えてきたように、このコロナが終息を迎えた時にも供養の碑が建てられるかもしれません。アマビエの石像と共に後世に伝えていってくれることでしょう。
お墓で楽しむ芸術の秋
2023年9月30日
こんにちは。愛知県豊田市の中澤⽯材店です。
だんだんと秋めいてまいりました。何をするにも気持ちの良い季節、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋…ですね。今日のお話は“お墓で楽しむ芸術の秋”です。お墓で芸術!?と思われるかもしれませんが、歴史上の人物や著名人が眠っているような古い大きな墓地は、特徴のあるお墓が多いものです。

特にそういう墓地が多い東京をのぞいてみると…例えば府中市にある都立多磨霊園。
ここは1923年(大正12年)に開園した、東京ドーム約27個分という広大な敷地を持つ緑豊かな霊園です。敷地内にはたくさんのお墓が並び、教科書に載っているような偉人や著名人が眠る墓所があちこちに点在しています。霊園が発行している霊園案内図には著名人の墓所の区画番号が一覧で記されているほどです。

霊園内を少し歩いただけでもドーム状のお墓、本を開いた形をした墓誌、胸像や観音像などいろいろなデザインのお墓が目にとまります。中でも個性的なのが、芸術家・岡本太郎のお墓。大阪・万博公園の太陽の塔や、「芸術は爆発だ!」に象徴される際立った個性はお墓にも発揮されています。墓碑はブロンズ彫刻の「午後の日」。真ん丸の目で、ほお杖をついて、いたずらっぽくこちらに笑いかけています。

また、画家・漫画家であった父の一平、作家であった母・かの子のお墓も同じ場所にあり、一平の墓碑は焼き物の「顔」という作品、かの子の墓碑は観音像です。3人のお墓は、小さなスペースを囲む形で向き合うようにたっていて、訪れる人たちを一家で温かく出迎えてくれているようです。
この秋は、晴れた日を選んで、お墓を散歩がてら芸術鑑賞はいかがでしょう。もちろん、他人のお墓ですから失礼のないよう、墓前のご挨拶は手短に。手を合わせたらそっと立ち去りましょうね。